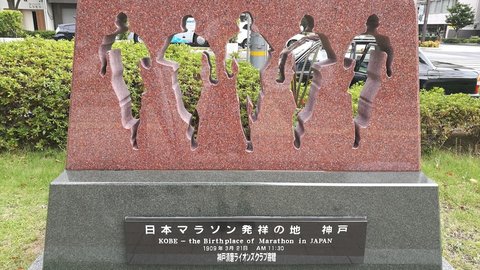他県には譲れん。地元が誇る、日本全国の意外な「発祥の地」
かつて1853年に神奈川県横須賀の浦賀に、黒船来航がきっかけで開国した日本。そこから西洋の文化が伝わり、明治にかけてグルメや産業など、さまざまな分野が発展・進化してきました。
なかでも横浜は「食パン」や「鉄道」、「ガス灯」の発祥の地としても知られています。しかし実は横浜だけでなく、ほかにも全国津々浦々に「発祥の地」がたくさん!
いまでは当たり前になっていることでも、知ってそうで知らなかった、意外なルーツをもつスポットも少なくないのです。そこで今回は日本全国にあるいろんな「発祥の地」についてご紹介していきます。
最後にアンケートもありますので、みなさんのジモトが誇る発祥の地についてもぜひ教えてくださいね。
※今回ご紹介する発祥の地のなかには、さまざまな諸説があるものもありますが、一般的に日本国内で伝えられているスポットをピックアップしています。
※お出かけの際は3密に注意の上、新型コロナウィルスの国内情報および各施設の公式情報を必ずご確認ください。
波乗りの発祥の浜/山形県

まずは海での人気アクティビティ「サーフィンの発祥の地」から。関東では神奈川県の湘南や千葉県の御宿、静岡県の南伊豆・下田がサーフィンのメッカといわれていますよね。
しかし意外や意外。波乗り、すなわちサーフィンの日本の発祥地は山形県なのです。
同県の鶴岡市にある湯野浜では、江戸時代に子どもたちが舟の板を使って、「瀬のし」と呼ばれる一枚板で波乗りする姿が目撃されています。
いまのようにサーフボードを使って波に乗るスタイルは1960年代にアメリカから伝わったとされるので、それよりもはるか昔に山形県ではサーフィンが行われていたのですね。
ちなみに湯野浜は1960年代に、日本海で初となるサーフィン大会がおこなわれています。
オセロ発祥の地/茨城県

誰もが遊んだことがあるといっても過言ではない、世界的に有名なボードゲーム「オセロ」。この「オセロ発祥の地」は、茨城県水戸市といわれています。
きっかけは同市出身の長谷川五郎氏が学生時代に考案したのが始まりなのだとか。もともとは製薬会社に勤務していた長谷川氏が、このゲームを取引先などで披露していたところ、医師に高く評価され、1973年に製品化。いまでは、世界中で人気のゲームとなりました。
温泉マーク発祥の地/群馬県

地図上で温泉や鉱泉の位置を表す「温泉マーク」。古くからお風呂や温泉を意味するマークとして親しまれていますよね。
時代をさかのぼること江戸時代。群馬県の安中市磯部で勃発した土地をめぐる農民間の争いが発生。その争いに決着をつけるため、江戸幕府から「上野国碓氷郡上磯部村と中野谷村就野論裁断之覚」という評決文が出されました。
この評決文に磯部温泉と記した温泉マークがふたつ記載されていたことから、「温泉マークの発祥の地」は群馬県といわれているのです。